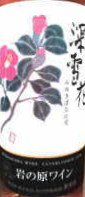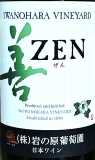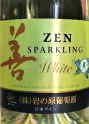岩の原ワイン 深雪花 新潟県上越市
〜日本ワインの源流、礎がここにあり!葡萄品種マスカットベーリーAが生まれた地〜
株式会社岩の原葡萄園 代表者 坂田敏氏
住所 新潟県上越市大字北方1223
創業年 1890年
年間生産量 約45万本
自社畑 約6ヘクタール


















【日本のワイン葡萄の父 川上善兵衛】が開いた老舗ワイナリー
岩の原葡萄園の創業者・川上善兵衛は、慶応4年(明治元年、1868年)、新潟県上越の地に生まれました。勝海舟を師と仰ぎ、その薫陶を受けた善兵衛は、「岩の原」の地名が表す通り、石だらけで痩せたこの地に暮らす農民の救済のため、師譲りのチャレンジ精神で、ぶどう栽培、ワイン醸造の事業を興したのです。明治23年(1890年)、善兵衛若冠22才のときでした。しかし雨の多い日本では醸造用葡萄の栽培は困難を極めたため、善兵衛は欧米から自費で多様な葡萄の苗木を取り寄せて品種改良に努め、病害虫に強く、日本の気候風土にも適したアメリカ種葡萄と、品質的に最ものぞましいヨーロッパ種葡萄を品種交配し、今日わが国の醸造用の代表的な葡萄品種となっているマスカットベリーAやブラッククイーン、ローズ・シオターなどの優良品種を生み出しました。また、醸造面では本邦初の密閉醸造や、越後名物の雪を雪室(ゆきむろ)で秋まで貯蔵し、ワイン醸造時期に冷却に用いることで、当時としては極めて珍しい低温発酵を可能にし、飛躍的な品質向上を成し遂げ、本格的国産ワインの礎を築き上げました。そうした功績から、善兵衛は「日本のワイン葡萄の父」と呼ばれています。「岩の原葡萄園パンフレットより」
とても思い出深いワイナリーであります。私が自分の意志で、ひとりで訪ねた最初のワイナリー。1991年、まだ、私が20代前半の若かりし頃、新潟の酒蔵を何軒か一週間ほどかけて巡ったことがあります。その当時、ワインの勉強もしていて、頭でっかちで知識欲が旺盛だった最盛期でもあったため、国産ワインの原点である“岩の原”は見ておきたかったのです(生意気ですね)。基本、日本酒の酒蔵を見学しに来ていたので、季節は、真冬。細長い新潟じゅうをみてきましたが、とくに上越のこの辺りは、ものすごく雪が深かった(今ほど温暖化してなかったですし)。道の両側には3〜5メートルほどもある雪の壁が立ちふさがり空を狭くし。さらに、低く垂れ込めた濃い灰色の厚い雪雲は、真昼間でも夕暮れ時のように、あたりを薄暗くしています。一寸いただけで、陰鬱な気分にさせられる雪国のこの地で、川上善兵衛翁はひと冬閉ざされたなか、テンションを下げることなく来春に向けての葡萄研究に余念がなかったのでしょうか。などと、思いをはせつつ、たどり着いた岩の原葡萄園は、当然、この季節に見学に来るお客さんもいず、私ひとりだけ。寒造りをする日本酒の酒蔵と違って、醸造期も終わっているし、葡萄畑も雪の下。まったく稼働しているところがありません。昔の記憶をひも解いて印象に残っているのは二点。ひとつは、ワイナリー石蔵内の静謐でピンと張りつめた、冷たく清浄な空気感。とても純粋で、気持ちが引き締まるような雰囲気。これ以降、他の、どのワイナリーにいっても感じることのないピュアな感覚がありました。もうひとつは、雪に完全に埋もれた自社畑の斜面。ワイナリーの方に「あそこが葡萄畑です」と、指を差されても、ただの雪山。しかも、北斜面であるといいます。日照時間が短く、葡萄畑として条件の悪い北斜面でも、立派に葡萄が出来ると証明し、農家の人を鼓舞するため伝兵衛翁はあえてあそこを自社畑にしたのです、と説明され感動したのを憶えています(実際は、農民救済が目的の事業を興すのに、農家の人の良い土地を取るわけにもいかず、自身の所有地であった北斜面を自社農園にせざるを得なかったというのが実情らしい)。そんな思い出のあるワイナリー。今度は秋に、葡萄が実っている畑を訪れてみたいものです。でも、昔に、深い雪に閉ざされた岩の原を見れたことは、この醸造所のある意味本質に触れられたようで、今となっては代え難い経験だったのかもしれません(現在では冬に行っても、あの頃ほど雪が積もっていないと思います)。
【マスカットベリーAなどのワイン用優良葡萄品種が誕生するまで】
●明治23年(1890年)6月、善兵衛は小作人の土地をとりあげることはせず、自宅の日本庭園を壊し、果樹栽培の試験園、葡萄の苗木試験地をつくり始めました。庭園はその家の顔であり、富裕を知る尺度でもあり、それを壊しだしたので、周囲の者は驚き、伝兵衛の決意のほどを知ったのです。川上善兵衛著「葡萄全書」では「予は先づ宅地内の庭園を毀ち、雑木を伐採し、仮山を削りて泉水を埋め、多数の大小奇石を一隅に堆積し、その土地を深耕して良圃となせり、この地、字“岩の原”なるを以って人称して岩の原葡萄園と呼ぶに至る」とあります。
●明治34年(1901年)当時で、葡萄畑が18.3ヘクタール、導入した葡萄の品種353種、葡萄畑に定植した株数は5万5570株におよんでいたといいます。品種の選択基準は、初期は栽培しやすい品種をおもに優良品種としていたのを、ワインにしたときの品質を優先するようになり、増殖して生産期に入った品種でも良いワインにならないものは伐採し植え替え始めました。伝兵衛は、品位優秀な葡萄品種を欧州種(ヴィニフェラ品種)系類とし、中位の葡萄品種を米国種(ラブラスカ品種)および交配種としました。また、別記として米国種のコンコードはただちに伐採し、アジロンダックなども徐々に植え替えするとあったそうです。そのことからも善兵衛の交配による品種改良の基本理念は、この地の気象条件下での欧州系葡萄品種に近い優良ワインを造るためであったことがわかります。
●大正11年(1922年)上記の結果から、日本の風土に適した品種改良が必要と決断し、独自の交配を開始。生涯において交配した数10311種、うち結実したのは1100種、栽培適性のないものは淘汰され、ワインにして優れた酒質のものを選び、合計22種を後に優良品種として発表するに至ります。
●昭和2年(1927年)マスカットベリーA、ブラッククイーンなど優良品種が生まれる。
〜サントリー博物館文庫「川上善兵衛伝」と「ヴィノテーク」から引用・参考にさせていただきました〜
葡萄品種マスカットベーリーAとは・・・・1927年頃に、新潟の川上善兵衛氏によってぺーリー種(母・ラブラスカ品種)とマスカット・ハンブルク種(父・ヴィニフェラ品種)から造られた交配品種。赤葡萄。「マスカット・ベーリーA」は、マスカット・ベリーAと表記されるのを多く見ますが、母親である「ベーリー」の英語表記は「Bailey」であり、日本語ではベリーではなくベーリーと表記したほうが、原音に近い。開発者の川上善兵衛は「マスカット・ベーリA」と表記していたとのこと。この葡萄品種由来の甘いイチゴ香(フラネオール=いちごの香りに含有されている物質)が、特徴的に有ります。
葡萄品種ブラッククイーンとは・・・・1927年頃に、新潟の川上善兵衛氏によってベーリー種(母)とゴールデン・クイーン種(父)から作られた交配品種。赤葡萄
葡萄品種レッドミルレンニュームとは・・・・1929年頃に、新潟の川上善兵衛氏によって未詳1号種(母)とミルレンニューム種(父)から作られた交配品種。薄赤(グリ)葡萄、白ワイン用
葡萄品種ローズシオターとは・・・・1927年頃に、新潟の川上善兵衛氏によってベーリー種(母)とシャスラー・シオター種(父)から作られた交配品種。白葡萄
9,350円(税850円)
2,497円(税227円)
2,497円(税227円)
2,497円(税227円)
1,496円(税136円)
1,496円(税136円)
1,870円(税170円)